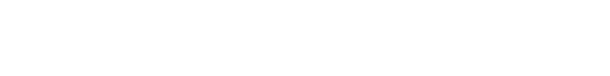広島別院とは
沿革
-
1459年(長禄3年)
武田山のふもとに建立され、龍原山仏護寺と称し、当時は天台宗でした。しかし、同寺第2世円誓は、本願寺第8代蓮如上人に帰依しました。
-
1496年(明応5年)
浄土真宗に改宗し、第3世超順のころ、毛利元就は仏護寺を護持しました。
-
1590年(天正18年)
毛利輝元が広島城を築き町割りをしたとき、仏護寺を広島小河内(打越)へ移転しました。
-
1609年(慶長14年)
藩主・福島正則が現在の地に移転させ寺町としました。
-
1902年(明治35年)11月
広島別院仏護寺と称しました。
-
1908年(明治41年)4月
本願寺広島別院と改称しました。
-
1945年(昭和20年)8月6日
原子爆弾の投下によって堂宇のすべてを消失しました。
-
1964年(昭和39年)10月
安芸門徒の懇念を結集して、現在の本堂が完成しました。
-
1994年(平成6年)
再建後30年目に、本堂を中心に大規模な修復工事を完遂し、広く門信徒の信仰の中心道場として、その役割を担っています。
安芸教区寺院マップ
安芸教区とは
浄土真宗本願寺派は「阿弥陀如来」を本尊とし
「南無阿弥陀仏」のお念仏を称えます浄土真宗本願寺派は、「阿弥陀如来」を本尊とし、「南無阿弥陀仏」のお念仏を称えます。宗祖は「親鸞聖人」です。 拠り所とする聖典は「浄土三部経」等があります。おつとめには「帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい)…」で始まる「正信偈」がよくつかわれます。 京都の本願寺(通称西本願寺)を本山とし、「お西さん」とも呼ばれています。

安芸教区には広島県西部
25組500ヶ寺余りの寺院が所属しています浄土真宗本願寺派(本派)では、全国を32のエリアにわけていますが、その一つ一つの区域の呼び方を「教区」あるいは「特区」と表現しています。「安芸教区」は、その32の教区・特区の1つで、その範囲は広島県西部です。各教区の名称は地域の歴史の中で呼ばれてきた名称が使われているため、必ずしも行政区域の名称と同じにはなっていません。安芸教区には広島県西部25組500ヶ寺余りの寺院が所属しています。

共命鳥について
共命鳥(グミョウチョウ)は、一つの身体に二つの頭をもつ鳥です。考え方、生き方が違っていても、そのいのちはつながっているという、鳥に姿をかえられた仏さまのみ教えを表しています。
「すべてのいのちの尊さや、存在を大切にしあう社会」のシンボルが共命鳥です。戦争をなくし、平和を願う安芸門徒のシンボルとしてかかげます。

共命鳥の説法について
『阿弥陀経』にお浄土に住む鳥の名前が六つ出てきます。その中に「共命之鳥」といい、美しい羽毛をもち、きれいな声で鳴く鳥がいます。体が一つで頭が二つある奇妙な鳥ですが、大切な法を説いています。
多くの共命の鳥の中でも、とりわけ素晴らしい鳥がいました。しかし、二つある頭のいずれもが「わたしの頭の羽毛は比類なく美しく、声も世界一美しい」と確信し主張し合いました。そして互いに憎みあい争うようになり、遂には「片方さえ亡きものにすれば、この私が世界一になれる」と考えるようになり、ある日密かに毒を混ぜ、片方に食べさせました。食べた方はもちろん死にましたが、食べさせた方も体が一つですから、死んでしまいました。
この愚かな事件があってから、お浄土の共命の鳥は「他を滅ぼす道は己を滅ぼす道、他を生かす道こそ己の生かされる道」と鳴き続けていると申します。これは鳥の姿に表された仏さまのみ教えであります。
条件が変われば何をするかわからぬ人間がつくっている社会であり、いたずらに対立をあおらず、常に他のいのちとのつながり、いのちのぬくもりを大切にと願わずにはおれません。
御同朋の社会をめざす運動
「御同朋の社会をめざす運動」(実践運動) 安芸教区総合基本計画(R6~R9年度)